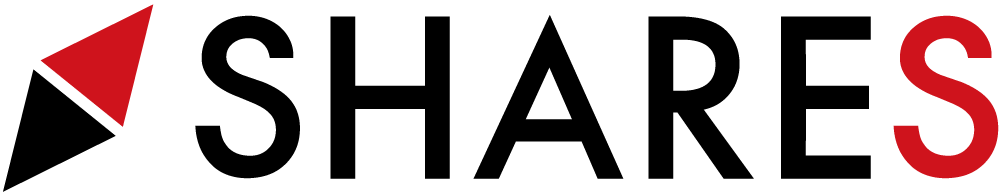サービス提供終了のご案内
2015年6月よりサービスを開始しました月額費用ゼロ!中小企業向け専門家スポット相談サービス|SHARES(シェアーズ)は2023年9月29日をもちましてサービスの提供が終了いたしました。
長きにわたりSHARES(シェアーズ)をご愛顧いただきましてありがとうございました。
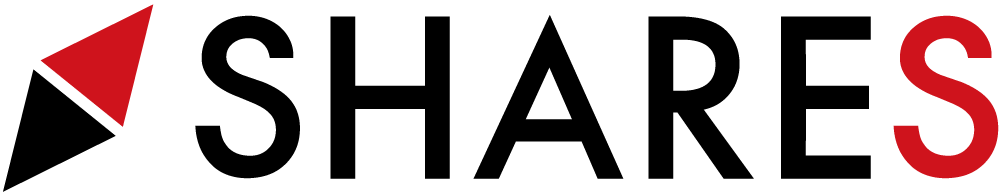
2015年6月よりサービスを開始しました月額費用ゼロ!中小企業向け専門家スポット相談サービス|SHARES(シェアーズ)は2023年9月29日をもちましてサービスの提供が終了いたしました。
長きにわたりSHARES(シェアーズ)をご愛顧いただきましてありがとうございました。